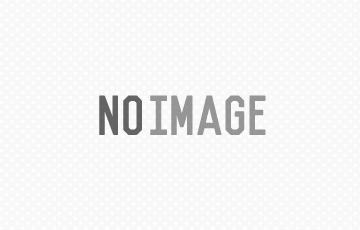丸山 淳子
ザンジバルには行ったことがない。とても美しい場所だという話はよく聞く。海が青くて、空も青くて、格調高い街並みが広がり、色とりどりの服を着た人たちが行きかっている。そんなイメージを持っているけれど、本当のところを、私は知らない。
そんなザンジバルの、とある家の庭先で、ゴザのうえにごろりと寝ころぶおばあちゃんのことを、育休中の私は何度となく思い浮かべていた。夕暮れに、とくに理由もなさそうなのに、ちっとも泣きやまない娘を一人であやしながら、そのおばあちゃんのことをずっと考えていた。娘と私しかいないマンションの一室で、その窓の向こうにみえる空の、さらにそのずっとずっと向こうにあるはずのザンジバルには、あのおばあちゃんがいる。一度も会ったことはないけれど。
自分が娘をもつようになるとは想像もしなかったもう15年以上も前のこと。「アフリカ便り」に寄せられた「子供とは、泣くものである(タンザニア)」というエッセイを、私は繰り返し読んでいた。そのころ、アフリックでは『アフリカで育つ』というエッセイ集をまとめていて、このザンジバルを舞台にしたエッセイは、そこに掲載するものの一つに選ばれていた。編集メンバーのひとりだった私は、このエッセイを担当しながら、つくづく良い話だと思っていた。赤ん坊が泣くことにだんだん動じなくなる筆者の様子も良いし、なにより、最後のおばあちゃんが良い。10人も子どもがいるのに「私は産んだだけだもの。あとは、放っといたら育っただけよ。」と言ってのけるのだ。
当時すでに、このエッセイは印象的なものだった。でも、それが、うんと鮮烈に私に迫ってきたのは、自分が娘を産んでからのことだった。赤ん坊は泣く。あたりまえだ。そんなこと、私だって、知っていた。産む前から知っていた。だけど、泣き続ける娘を前にすると、うろたえた。そして、娘の泣き声に耳をふさぎたくなる自分にとまどってもいた。ああ、どうしたら、あのザンジバルの母たちのように、おおらかな気持ちになれるのだろう。
私の調査地であるカラハリでも、こんなふうに追い詰められた気持ちになったことはなかった。あそこでは、子どもを産んだことなどなくても、赤ん坊の世話は当然のようによく任された。背中に赤ん坊を括り付けて、調査をしていたときもあった。だけど、赤ん坊が泣いても、まぁいいや、と思えたし、そもそもちっとも泣きやまずに困ったというような記憶もない。なにせ、赤ん坊がちょっとでもぐずると、すぐにみんな集まって、なんのかんのとかまってやるのだ。あっという間に、赤ん坊はすっかりご機嫌をなおす。赤ん坊の母親は、その様子を気に留めているふうでもなかったし、そもそも授乳のとき以外は、赤ん坊のそばにいないことだって多かった。まさに「放っといてる」状態だったのだ。

写真1 子どもに、ごはんを食べさせるのは母ではなく、訪ねてきたおばさん

写真2 ティーンにとって、親戚や近所の子どもの世話は、ごくありふれた日常