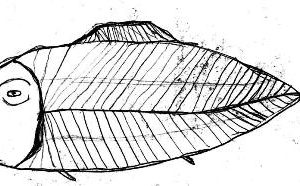アフリカの熱帯雨林に暮らす狩猟採集民ピグミーは、歌と踊りをこよなく愛する人々として知られている。日が沈み、森に囲まれた小さな村に月が顔を出す頃、どこからともなく太鼓の音が聞こえ始める。夕食を終えた女性たちは広場に集い始め、その美しい歌声を村に響かせる。女たちの歌声が少しずつ大きくなるのを待ちきれないとでもいうように、子供たちは広場に駆け出し、はじけるように踊り出す。踊りは子供だけでなく、男性の名手やときに個性豊かな精霊が登場して繰り広げられる。ピグミーの歌と踊りの種類は豊富で、彼らは毎晩のように歌と踊りに興じている。彼らが奏でるポリフォニー(多声音楽)はいくつものメロディやリズムが同時に展開していくというもので、古代エジプトのファラオから現代の音楽家や研究者にいたるまで数多くの人々を魅了してきた。私も例外ではない。大学院でアフリカの森へ行くことを決心したのは、CDで聴いたピグミーの歌声が忘れられなかったからでもある。

踊りの衣装をつけた子供たち
カメルーンの熱帯雨林でピグミー系の狩猟採集民バカの調査を開始して数ヶ月ほど経ったある日、私の怒りはついに頂点に達した。私は、森の小道ですれ違ったバカの男性サンゴンゴに向って、「あなたたちは口を開けば、石鹸、石鹸という。朝も石鹸、昼も石鹸、夜も石鹸。村でも森でも石鹸だ。石鹸しか言えないの?そんなことばかり言うあなたたちは私の家族ではないし、友達でもない。私の家にはもう来るな!」と怒鳴りつけた。突然烈火のごとく怒り始めた私に唖然としているサンゴンゴと、植物採集に出かけるために小道をともに歩いてきた女性モボリを残し、私は一人で足早に村へと帰っていった。土壁とラフィア椰子で出来た家に戻ると、土壁にはりついている小さな二つの窓と形の歪んだ閉まりの悪い戸を荒々しく閉めた。部屋のなかに瞬く間に闇の世界が広がった。ランプを灯した後、私はしばらく椅子に座っていたが、憤りはなかなかおさまってくれない。靴を脱ぎベッドに体を横たえた。すると、森から帰ってきたサンゴンゴとモボリの声が聞こえてきた。森での私の様子を村の人に語っているのだろう。村の人たちの相槌や驚きの声が、草葺きのドーム型住居の立ち並ぶ村のあちこちから聞こえてきた。興奮した人々の会話を聞き取ることは難しく、「シホ(私の名前)」や「スクラ(石鹸)」、「ジェレ(興奮)」という言葉が頻繁に繰り返されていることはわかったが、彼らが私の言動についてどう語っているのかはわからなかった。しかし、もうどうでもよかった。なんと言われたっていい。ともかく彼らの顔を見ていたくない。明日、荷物をまとめて街へ出よう。ここからブッシュタクシーが来る村まで40kmほどあるが、2日間も歩いたら着くだろう。その先のことはそれから考えればいい。ランプの明かりを頼りに、私は暗闇のなかで荷造りを始めた。
私が調査を行っているバカの村は、カメルーンの東南部の森林地帯のなかでもとくに辺境に位置している。彼らは森の動植物や農作物を食料や道具類の材料にするとともに、商人と森林産物を交易することによって得た工業製品を利用しながら生活を営んでいる。町から遠く離れたこの村に交易にやってくる商人の数は少なく、村の人が工業製品を入手する機会はたいへん限られている。彼らは鍋や衣類、石鹸など工業製品の不足について語るものの、それでもこれらのものが無ければ無いで、村内で貸し借りをしながら、また森の動植物を材料に作った道具類で間に合わせながら暮らしを立てている。そのようななか、村に突然現れ調査を開始した私が、お礼にと石鹸を配り始めた。大きなたらいにいっぱいの水を汲んでもらったら石鹸を一つ、焚き木をとってきてもらったら石鹸を一つ、野生のヤマノイモやハチミツを分けてもらえばそれぞれ石鹸を一つというように、ことあるごとに私は石鹸を渡した。そしていつの間にか彼らのなかで「私=石鹸をくれる人」という認識が出来上がり、私の顔を見ればみな口をそろえて「石鹸が欲しい」と言うようになった。
朝、まず食事の調査のために村内を回れば、皆くちぐちに「石鹸」という。村や森を歩いている時、ばったりと出会えば「石鹸」という。調査の合間に家でくつろいでいると、戸口からひょっこり顔をのぞかせて「石鹸」という。さらに、収穫物や夜の食事の調査のときも、こりずに「石鹸」という。そのうち、村の住人だけではなく、噂を聞きつけた近隣の村の人々が家にやってきては、「石鹸」というようになった。世話になっている人に対してどのようにお礼をしたらいいのか戸惑いながら、慣れない調査に神経をすりへらしていた頃である。日本では経験したことのない面と向っての無心に対して、私はうまく対応できず、村の人たちとのコミュニケーションに悩んだ。石鹸が村に無いのはわかっているし、出来ればみんなにあげたいが、みんなにあげるほどは持ち合わせていない。お世話になっているという感謝の気持ちと石鹸の残存量というどうしようもない問題、さらには石鹸のことばかり話す人々への不満が私のなかでうずまいた。気持ちを伝えたほうがいいのではないかと思うこともあったが、車やバイクを乗り継ぎ最後は徒歩でやっと見つけた調査村である。村の人たちに嫌われるのが怖くて、怒りや不満をぶつけることが出来ないまま、私は朝から晩までの石鹸攻めに疲れ果てていった。疲れが頂点に達していた時、森の小道でサンゴンゴに出会った。彼がいつものようにのんきな調子で「こんにちは、シホ。石鹸が欲しいな」と言った瞬間、私のなかで積もり積もった怒りと不満が爆発したのである。
私は荷造りを終えると、水浴びには行かず、少し早めの夕飯をバナナと缶詰ですませた。夕方になり、森や畑に行っていた人々が次々と帰ってきているのだろう。収穫物を入れた籠や焚き木を下ろす音にまじり、人々の話し声が聞こえた。いつもなら、収穫物の調査を行うために慌てて村中を回る時間である。しかし、その日は調査どころか外に出る気にもならず、私は寝袋のなかにもぐりこんだ。しばらくの間、頑な心とともにベッドに横たわっていると、外からは焚き火のはじける音と夕飯の匂いが流れこんできた。村は活気を取り戻し、広場で遊んでいる子供たちを呼ぶ母親の声や子供たちにいじめられて心細げに鳴くイヌの声、酒につぶれ大声でわめく男の声やその様子にクスクスと笑う女の声が満ちていた。家族がともに食事をとりながら、今日一日村や森であったことを語り合う人々にとって最も心休まる時間がまさに訪れようとしていた。私が森でサンゴンゴに怒鳴った後、家に閉じこもっていることも夕飯の話題となるのだろうか、それともそんなことはすでに忘れて何かもっと愉快な話をしているのだろうか。ゆっくりと揺れるランプの光を見つめながら、私は自分一人だけが別の世界の住人であるかのように感じた。無理やり眼を閉じ眠気が訪れるのを待ったが、昂ぶった心では安穏の世界が訪れてくれるはずもなかった。

太鼓の練習に励む子供たち
突然、太鼓の音が家の前で鳴り響き、力強い太鼓の音にのせて村の女たちが奏でる歌声が聞こえきた。繊細な歌声が幾重にも重なり合い、やがて村中に響き渡るほどになった。私は何が起こったのかわからず、家をゆらすかのごとくに響く太鼓と歌声を呆然と聴いていた。しばらくして、はっとした。村の人は、歌と踊りで私を家から出そうとしているのではないだろうか。私は歌と踊りが好きである。さすがに広場で毎夜のごとく行なわれる歌と踊りのすべてに参加することはできないが、彼らの歌を聴きに広場に出る夜は少なくない。ときに、彼らと一緒に夜遅くまで歌い踊ることもある。調査を始めたばかりの頃、彼らの歌と踊りが見たくて、夕方になるとつたないバカ語で「今日は歌と踊りは無いの?」と聞いたものだった。そう尋ねた日は、必ずといっていいほど村の人たちは歌い踊ってくれた。村の人は私を歌と踊りに参加させるために、舞台を広場から私の家の前にうつし、歌と踊りに興じているのではないだろうか、そんなふうに思えた。家の前で踊りの名手が体を揺するたびに、体につけた楽器がリズミカルな音を刻む。姿は見えないが、戸を一枚隔てたむこうでは、高まる太鼓の調子と女の歌声に合わせて、踊り手が激しく踊っている様子がありありと想像できた。
私は寝袋から抜け出し、窓をそっと開けてみた。しかし、暗くて外の様子は見えない。とうとう我慢ができなくなり、私はランプを持って戸口から飛び出した。村の人たちは、部屋から出てきた私に気にも留めない様子で歌い踊り続けていた。ランプの光が、私の家の前を行ったりきたりしている踊り手の姿を闇に映し出した。サンゴンゴだった。サンゴンゴは腰に植物の飾りを羽根のようにつけ、筋肉でたくましく盛り上がった上半身をあらわにして踊っていた。私はサンゴンゴの近くにランプを下ろし、歌い手のなかにまじって踊りを見つめた。サンゴンゴは、ランプの周りやランプを股の下にくぐらせて一心に踊った。明かりを楽しむように踊るそのユニークな様子に歌と踊りはますます盛り上がり、私はいつの間にか女たちの歌に加わっていた。人々の楽しそうな様子を見ながら声を張り上げて歌っているうちに、自分があれほど気にしていた石鹸のことが急にバカらしく思えてきた。もし私が、彼らの立場だったら同じことをしただろうな、そんなふうにも思えるようになった。明日また「石鹸」と言われても、もう怒ることはないだろう。笑って、「今度また持ってくるね」と答えられるだろう。私はその日、久しぶりに夜が更けるまで村の人々と歌い踊った。
ピグミーが歌と踊りをこよなく愛する理由の一つは、歌と踊りがかたく閉ざされた心を解き放ち心と心をつなぐ力を持つからではないだろうか。彼らは、森の世界に突然現れ人々とのコミュニケーションに行き詰った私を歌と踊りで慰め、行き場の無かった怒りや心をさいなんでいた孤独感をみごとにやわらげてくれた。私はアフリカの森で経験した歌と踊りにまつわるこの出来事を通して、ピグミーにとっての歌と踊りは、他者に対する優しさがつまった仲直りの魔法であるのかもしれないと思うようになった。コミュニケーションの達人ともいえる歌と踊りの民は、あの夜以降「石鹸」の話をしなくなり、私は合計2年間近くの調査をピグミーとともに歌い踊りながら続けさせてもらっている。日本での生活があるので、彼らとともにいつも歌い踊っていることはできないが、今夜もまた、アフリカの森にはピグミーの歌声が響いているに違いない。