大石 高典
さかなの炭火焼きとマニオクちまき(注)の組み合わせは、カメルーンの都市部で、もっとも安く、手っ取り早く、かつ美味しく食べられる外食の典型である。それぞれ、共通語であるフランス語で、”poisson brais”(ポワッソンブレゼ…なぜか”poisson grill”とは呼ばれない)、”batn de manioc”(バトンドマニオック)と呼ばれる。少し時間とおカネに余裕があれば、これに冷え冷えの瓶ビールを買って一緒に食すのが最高である。
夕飯時ともなれば、首都ヤウンデの交差点やバーの近くなど人の集まる街角のあちこちで、ドラム缶を加工した七輪に炭火を熾して魚を焼く女性たち,その周りで焼き魚の品定めをしたり、ビール片手に友人と食事をとる客たちを見ることができる。ぶつ切りにされた焼き魚の切り身は大きさや部位によって値段が異なるが、1切れ300FCFA(現在のレートで50円)くらいから買うことができる。解凍され、切れ目を入れられた魚は、焼く前にマギー・ブイヨンを溶かした塩水に漬けられる(魚の仕込みにはいくつも流派があるようである。こだわりのある人は、自分の家で調理する)。炭火がよく熾ったらば、売り手の女性は客の入りを予想しながら網の上に油を塗った魚を並べてゆく。いい切り身は、客の間で競争になるので早めに露店を見て回って、予約しておくのがよい。値切り過ぎると、他の客に切り身を取られてしまうので要注意である。焼き上がった魚は、露店ごとに自家製の唐辛子ソースをたっぷり添えて、タマネギのスライスをトッピングされて客に供される。焼き立てのアツアツを、これまたピリピリのソースにつけてつまみつつ、キャッサバのちまきをごはんにするのである。この焼き魚は、やはり手で身をむしりとりながら、タマネギのかけらと一緒に食べるのがうまい。

街頭で魚を焼く男性。
焼き魚は、大都市でも地方都市でも見ることができるが、焼かれる魚の種類は地域によって異なる。大西洋岸沿いのクリビやリンべでは、漁師さんがその日に獲ってきた多様な海水魚が焼かれている。オニカマス(バラクーダ)の焼き物はなかなかボリュームがある。首都ヤウンデでは、海に近い経済都市ドゥアラから冷凍にされた海水魚が運ばれてくる。街角で見られる魚種のほとんどは、なぜか「サバ」(マケロ“maquereau”)と呼ばれるアジである。

市場で売られている冷凍アジ
街頭ではまず見かけないが、焼き魚専門のレストランに行くと、これに巨大なスズキ(バール“bar”)やシタビラメ(ソル”sole”)などが加わる。客は、レストランの店頭で、売り手の女性と値切りの交渉をしながら大小さまざまに並べられた中から意中の魚を選び、焼いてもらう。50cm以上にもなる巨大なスズキやシタビラメの焼き魚が皿に乗ったさまは壮観であり、気の置けない仲間と食べる食味も最高だが、このような大きな魚になると、ポワッソンブレゼも値が張って庶民にはなかなか手が出せない贅沢料理となる。

大皿にのったポワッソンブレゼ(スズキ)とマニオクちまき。ヤウンデ市内のレストランにて。
私は海から遠く
離れた熱帯林地域の農村で研究をしているが、幹線道路の整った首都から地方に向かうにつれ、次第に、冷凍の海水魚は手に入りにくい、高級な食材となってゆく。首都では安い動物性たんぱく質源の代名詞とも言えるような冷凍海水魚は、森の世界に入ってゆくにつれ値段が高くなり、露店で見かけなくなってゆく。そして次第に増えてくるのが、近くを流れる河川で獲れるナマズ類やコイ類、そして最近普及しつつある養殖漁業によるカワスズメ類といった淡水魚の切り身を焼いたものである。運が良ければ、”Capitaine d’Eau douce”(キャピテンドゥオードゥース)と呼ばれるナイルパーチ(Lates niloticus)の切り身が食べられるかもしれない。森林地帯でポワッソンブレゼにされるのは主に大きめの魚で、小型の魚はクズウコン科植物の葉でくるんだ包み焼きにされる。
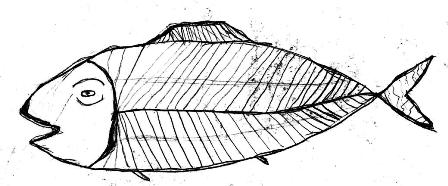
あるバクウェレの少年によるさかなのイラスト。鱗を、葉っぱのように表現するのが特徴的である。
焼き魚への嗜好は人さまざまだが、どの魚を選ぶかには匂いが重要であるようだ。淡水魚には、冷凍のアジにはない甘みがあって大変うまいのだが、都会から来た人の中には「泥臭い」という理由で食べない者がある。そして、逆に森の人の中には、冷凍アジを「腐った肉のような匂い」がすると言って食わない者がある。森の世界と都会を行き来するうちに、私の嗅覚も変わってきた。現地食主義の生活を終えた「森棲み」の身体で都会に出て行くと、食欲をそそるはずの海水魚が焼ける匂いがどうにも生臭くてたまらなく感じられてしまうのである。
注:有毒キャッサバを、水につけて発酵させた後に、クズウコン科植物の葉でくるんで蒸すと、ちょうどコメでつくり、葉ごと蒸した日本のちまきのような食べ物になる。くるみ方によって多様な形状ができ、それぞれに名前が着いている。
















