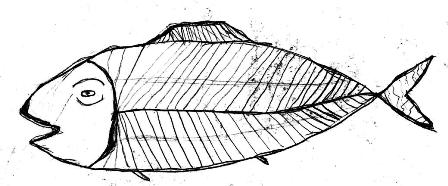目黒 紀夫
ウシ牧畜民マサイの人びとが多く暮らすケニア南部で調査をしていて幸せを感じる瞬間・忘れられない場面として、集落近くの草むらでみんなで輪になって、その日に屠畜されて調理された焼き肉(元は誰かの家畜)を食べていたときというものがある。
一般に牧畜民とは、ウシやラクダ、ヤギ、ヒツジなどの家畜を飼育・繁殖させては、それを生活の基盤として暮らしをなりたたせている人びとのことを指す。牧畜民といっても季節的・部分的に農耕や狩猟、採集といった生業活動をおこない、最近であれば賃金労働者や公務員になる者も珍しくない。とはいえ、1つの世帯がウシを100頭以上、ヤギ・ヒツジは200頭以上もっているなどというと、日本で会った人に「(牧畜民もそこで調査しているあなたも)毎日肉ばかり食べているんでしょ?」といわれたりもする。
しかし、実際のところとしては、家畜は牧畜民の人びとにとって一種の貯金であって、おいそれと殺して食べるような代物ではない。たとえば、観光ホテルの警備の仕事が月給約6,000円、農夫や牧夫としての雇用労働の月給が約2,000〜3,000円の僕の調査地にあって、肥えたオスウシ1頭の価格は20,000円を超えることもある。その一方で、放牧中に行方不明になったり病気で急死したり、あるいは旱魃で水・餌が不足して死んでしまったりする危険性もあるわけで、家畜の財テクはけっして容易ではない。だから、多くのマサイの人びとが自分の家畜から採れたミルクで毎日ミルク・ティーをいれているとはいっても、2005年から調査のたびにホーム・ステイしている住民の家で、僕はその家の家畜を屠畜して焼き肉にして食べさせてもらったことは実はまだ1度もなかったりする(たまに町の肉屋で買った少量の肉が出されたり、僕が肉を買ったりすることはあるが……)。

大旱魃で肉が完全に落ちてしまったウシ
とはいえ、これまでのところ、調査をしていて地域を歩き回っていると成人式や結婚式、葬式といった儀式に遭遇して、そこで食事に招待されてたらふく焼き肉を食べたことが2回ほどある。そうした場合、家畜の屠畜は数人の青年が少年や老人に見守られながらおこなう。どの肉の部位を誰が食べるかはあらかじめ決まっており、青年は器用に肉を切り分け、そして部位ごとに取り分けていく。そうした作業のさなか、青年たちは今切ったばかりの肉の切れ端を生のままでひょいっと口に放りこんだりしている。普段であれば料理は女性の担当だが、このときばかりは逆に、女性は調理現場のまわりでは見かけない。
脂身は鍋で炒められるが、そこで使われる油の量は日本人が「炒め物」という言葉で連想するよりもだいぶ多い(さすがに「揚げ物」とまではいかないが)。また、家畜の血を利用してスープが作られたりもする。そして、メインディッシュというべき赤味の肉(普段から運動をしている家畜の肉なので脂身は日本のそれと比べてだいぶ少ない)はというと、木の枝に刺さった状態で火の周囲に立てられ直火焼きとなる。焼きぐあいを確認しつつときどき肉の向きが変えられ、全体がまんべんなく焼けるようにされる。肉が焼けてくるにしたがい香ばしい匂いが立ちこめてくるが、肉の焼ける音と匂いは僕の食欲をいやがおうにも高める。

ウシを解体し焼く準備をする男たち
こうして焼けた肉の味つけは塩だけである。噛みしめるほどに味がしみ出してくる引き締まった肉を食べていると塩以外の味つけは余計に思えてくるし、日本に帰ってきてから普通の鶏肉料理を食べると「あれっ?」と思ってしまう。ここで、肉は焼けた塊から一切れずつ切り落とされてはその場にいる人たちに順番に手渡されるのだが、マサイの人たちは飲み物も飲まずにひたすらに肉を食べつづける。僕がはじめて参加したときは8人ほどで1つの肉塊を相手にしていたのだが、とにかくみんな食べるのが早くてびっくりした。噛みきれない肉塊に悪戦苦闘していると、肉の分配が一回りして次の塊が突きつけられる。目を白黒させながら「今はパス」といっても周りからは「取れ取れ」といわれて手に取るわけだが、そこでもたもたしていたら手のうえの肉塊がさらに増えてしまう……。
実は焼き肉じたいはケニアの首都ナイロビだけでなく、調査地の町にある肉屋でも食べようと思えば食べられる。ただ、何度か調査の最後の打ち上げにひとりで焼き肉を食べにいって痛感したのは、フィールドにおける焼き肉が僕にとって忘れられない思い出なのは肉が単に「おいしい」からではなく、おいしいものをみんなで一緒に「楽しく」食べるからなのだということだ。それ以来、知り合いを肉屋に招待したり大量の肉塊を買って帰って家の人に調理してもらったりするようにしているのだが、これまでさんざんお世話になっているわけだし、そろそろいい加減にウシを丸々1頭買って帰ろうかと思いはじめている。とはいえ、家畜市で「おいしい」ウシを見抜く眼力が僕にあるのかはかなり疑わしいし、まずはそのあたりから友人に相談せねば。

週に1回町で開かれる家畜市