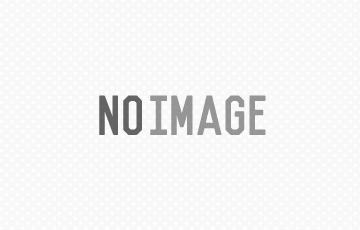紛争後の未来世代
僕の調査地であるコンゴ民主共和国はアフリカ大陸のほぼ中央に位置している。アフリカ第二位の面積を誇る広大な国土、世界有数の熱帯雨林、全長4700キロを超えるコンゴ河、多様な動植物など多くの探検家を魅了した始原の世界が今も手つかずのまま残っている。しかし、そうした自然の恵みとは裏腹に、むしろこの国は紛争国として人々に強い印象を与えているように思う。ルワンダ虐殺に端を発したコンゴ東部紛争では500万以上の人命が失われたと言われ、2012年に発生したM23の武力蜂起は日本の新聞各紙の一面で取り上げられた。
過激な情報ほど人々の注目を集めやすい。センセーショナルな主題であればあるほど興味を引ける。ただ、そうして拡散するイメージには、そこに生きる人々の表情が抜け落ちている。サハラ以南のアフリカはもっぱら危機や混乱というレッテルが貼られるばかりで、僕らと同じように生き、生活する人々の姿は充分に描かれてはこなかった。そこで、本稿では、僕が見てきた現地の情景と紛争後の社会を生き抜く人々にスポットをあてたい。
確かに、紛争がこの国に与えた影響は大きい。正直に言ってそれはなまやさしいものではない。コンゴ東部では各地の道路が寸断され、橋はおち、陸上輸送網が根こそぎ破壊され、以前のようなトラックによる換金作物の買い付けは不可能になった。そのため紛争後の世代は、片道300キロにおよぶ徒歩交易を余儀なくされている。彼らは子どもたちの学費や医療費を捻出するため、数十キロにもなる干し魚や獣肉などの内陸産品を背負い、森のなかを10日以上にわたって歩き続ける。満足な休息をはさむことなく、夜はヤブ蚊に苛まれ、雨に降られても、樹海を進む(写真1)。その様子に直面するたび、紛争の災禍がいかに過酷なものなのかを思い知らされた。

写真1 森林内部の徒歩交易
そんなことは不可能だ
翌16年10月、1年の準備期間をへて、ふたたびトポケの土地を訪れた僕は、村の人々とともに橋再建への第一歩を踏み出した。それまで培った人脈を総動員し、橋の設計を行うエンジニアやチェーンソーを扱うマシニストの協力を仰ぐことができた。それでも先行きは全くみえなかった。そもそも村人が橋の再建に成功した事例が存在していないのだ。道路整備を管轄する省庁での聞き取りでは、「そんなことは不可能だ。住民たちは途中で投げ出すだろう」という返事に肩をおとした。実際に森の木を切り、必要になる仕事量がリアルに感じられるようになると、とんでもないことをはじめてしまったという思いに打ちのめされた。
熱帯林の奥深く、チェーンソーの甲高い音が響いてくる。伐採サイトに向け、農道を迂回し森林地帯へ足を踏み入れる。村の境界を過ぎると無数の樹木が群生し、灼けつくような日差しは和らぐ反面、熱帯林の圧力に困惑させられた。方向感覚は定かでなくなり、チェーンソーの音だけを頼りに進まなければならない。農道から数百メートルも歩くと乾いた大地は無くなった。森林内部を縦横に走る小川に膝下まで浸かり、絡みついてくるツタを両手で払いのけ、ただ前に進む。川底にひそむ泥穴を踏み抜かないように慎重に進まなければならない。腰までハマってしまう穴がそこかしこにあるからだ。不安定な足場に翻弄されながら、バランスを崩しつつもどうにか歩き続ける。ジャケットの背中には汗の跡がじんわりと浮かんできた。
「この時期に橋の材木を取るのは反対だ」マシニストの言葉が重くのしかかってくる。橋に用いられる木材は森の奥のしめった土地でしか取れない。釘を打つことも困難な硬くて重い木を数百という単位に裁断し、雨期に入り水かさの増した森林内部から運び出さねばならない。限られた日程のなか、そんなことが果たして可能なのだろうかという疑問と格闘しているうち、伐採サイトに辿りついた。そこには優に30メートルを越える大木がそり立っていた。チェーンソーが唸りをあげ、マシニストは真剣な表情で木の根元部分に切り込みをいれていく(写真2)。回転するチェーンソーの刃から摩擦のためかときおり火花があがる。鼓膜をつんざく轟音と共に、ガソリンエンジンから漏れる白煙で周囲は包まれ、飛び散る木片の一部が危うく眼に突き刺さりそうになった。

写真2 大木を切り倒す
橋を架ける
橋の再建には、おおまかに木材の裁断と搬出、そして組み上げという三つの工程がある。言葉にしてしまえば簡単だが、その作業すべてを腕一本で行うとなると話は変わってくる。ようやく切り倒した大木を裁断するにも凄まじい労力がかかった。伐採サイト周辺の木々を手斧でなぎ払い、作業スペースを確保する。足場の悪い作業場で丸太を転がし、楔を打ち込み固定する。15人ほどがテコや素手をもちいて丸太と格闘するも全く動く気配がなかった。方々からテコをさしいれ、材木の重心を探り、水平が得られるまで微調整を繰り返す(写真3)。どうにか丸太を安定させ、廃油にひたした糸で線を引き、日が暮れるまで裁断を続ける。それでも作業初日はほとんど進捗がなく、かろうじて三枚の材木を切り出すのがやっとだった。

写真3 丸太を固定する

写真4 裁断の様子
なぜこれほどのエネルギーを投じられるのか。強い印象に残ったのは彼らの「僕らは充分に待ったよ、何も変わらない」という言葉だった。紛争が終結して十有余年、政府は未だ機能しておらず、生活基盤は崩壊したまま放置されている。誰かがこの状況を変えてくれる、そんな甘い期待はとうの昔に消えさった。自分たちの持つ限られた資源のすべてを使って生活を取り戻すよりほかない。そこにわずかでも可能性があるなら、彼らは全力で取り組んでいく。たとえ不可能と思えることであっても愚直に一つ一つ行動を積み上げる。
製材・搬出の目処が立ち、組み上げの準備にとりかかった。橋を組み上げるためには、川底を露出させなければならない。彼らは森からとったツタを組み合わせて川の両側面を覆い、その上から盛り土をして水路をふさいだ(写真5)。その後、家々からもちよった鍋を片手に残った川の水を手作業でかきだしていく。うっすらと川の底が見え始めた午前1時過ぎ、疲労がピークに達したタイミングで、折り悪く天候がくずれ雨が降り出した。みな全身ずぶぬれになりながら、延々、川の水と格闘する。雨に打たれ体は冷え切り、指先から感覚がなくなった。それでも作業を進める。「俺たちは兵隊だ」と軽口を叩き、仲間の士気が下がればトポケ独特の冗談が飛び交った。ようやく空が白み始めた頃、彼らは基準となる四本の支柱を据えつけることに成功した。話を聞いた時にはとても信じられなかったけれど、彼らは丸一昼夜かけて内陸地域への車両通行を阻むオシェミ河の流れを変えた。

写真5 水路をふさぐ

写真6 橋を架ける