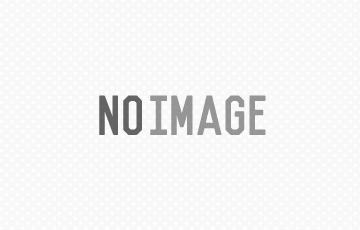森と河をつなぐ―コンゴにおける水上輸送プロジェクトの挑戦
コンゴ民主共和国でフィールドワークを続けてきた私たち3人(松浦直毅、山口亮太、高村伸吾)は、困難な生活を乗り越えようと血のにじむ努力をしている森林地域の人々の姿を目の当たりにし、彼らの取り組みを後押しするためにひとつの企画を発案しました。それが水上輸送プロジェクトです。
2017年夏、地域の人々と私たちの協力のもとでプロジェクトが実施されました。その一部始終をご紹介いたします。
ヤリサンガにて
松浦さんがワンバ村でプロジェクトのための船やガソリンの準備に奔走している頃、僕は、隣のイヨンジ村のヤリサンガという集落で森のキャンプでの調査に向けて準備を進めていた(写真1)。第2回で記したように、ボンガンドの人びとは、焼畑農耕に主軸を置きながらも、狩猟・採集・漁撈など複数の生業を組み合わせながら生活しており、それらの活動は、彼らの居住空間を取り巻く広大な森の中で行われる。僕はこれまで村落周辺での生業活動について調査を行ってきたが、森と村の二重生活を送るボンガンドの人びとの生活を理解するために、ぜひとも森のキャンプで調査を行う必要があった。そこで今回は、森の中の活動拠点であり、年に1~2ヶ月、人によっては数ヶ月にわたって利用することもあるという重要な森のキャンプで調査することを計画したのである。

写真1.ヤリサンガに木村さんが建てた家。現地の人びとと同じ材料、同じ建築方法で建てられている。
ちなみに、今回に限らず、集落に到着するとまず住民たちとの間で相談の場をもつことになっている。参加者は主に大人の男性であり、40人以上になるのが普通である。女性が参加していることもあるが、子どもは念入りに追い払われる。主な議題は、われわれ日本人調査者の近況報告、調査の予定とそれに伴う雇用機会の有無、最後に集落への支援についてである。この集落で長く調査を続けている木村さんは、住民への支援として、小学校へのトタン屋根の寄贈や高校生への学費の援助などを行ってきている。今回の集会では、住民の要望から高校生への学費の支援を取りやめ、そのかわり人数を絞って大学生への支援を行うことになった。しかしながら、被雇用者や学費の支援対象者の選定は、父系親族集団のあいだの利害が露骨に衝突するため、毎回紛糾する。われわれも限られた予算の中で研究と住民への支援をおこなっており、仕事の量や支援の範囲には敏感にならざるをえない。彼らの議論を放っておいたら、いつの間にか被雇用者や支援対象者が2倍になっているというようなことがままあるためである。そのため集会はいつも真剣勝負で、今回も仕事と学費の増減をめぐって、住民たちとわれわれの間で丁々発止の議論が繰り広げられた。このような集会が重要なことは重々承知しているが、われわれにとっては住民からの突き上げにさらされるという意味でやや憂鬱な場でもある。そのため、会場いっぱいに集まった男たちを眺めながら、ゾロゾロと連れ立ってやって来てうっとうしいなぁとつい思ってしまう。しかし、普段はあまり大声を出さないおじさんまでが口角に泡を飛ばしながら元気に議論している様子や、子どもたちがこっそりとその様子を眺めに来ては追い返されているところを見るに、彼らにとってはこういうやりとり自体もまたエンターテイメント的な側面を持っているのだろうと思う。
ともあれ、住民との相談は無事に終了し、今回調査を行う森のキャンプの選定もすんだ。準備万端、これでようやく調査に行くことができる・・・かというと、まだやらなければならないことがある。ヤリサンガの隣の集落に住む、イヨンジ村の村長に挨拶に行かなければならない。村長はイヨンジ村の行政的な責任者であり、われわれ調査者の動向を把握することがその職務に含まれることになっているため、ないがしろにはできないためだ。しかし、村長と会うのは気が進まない。村長は管轄する村の住民に対して大きな権力をもち、村の物事の決定やもめ事の仲裁などもある程度は彼らの裁量に任されている。ところが、選挙で選ばれるわけではなく特定の家系で代々世襲されており、よほどのことがない限り罷免されることはない。そうすると、どうなるか。おおよそ想像がつくかと思うが、村長をやっている人物は横暴で横柄な、ちょっと困った性格である場合が多いのだ。困った性格の人が村長職に選ばれやすいのか、それとも村長職が性格に影響を与えるのかよく分からないが、僕は後者だと思う。イヨンジ村の村長は、数年前に若い女性に代替わりしたが、ことあるごとに根拠のない現金の要求をするなど、早くも困った人物としての頭角を現し始めている。ヤリサンガの住民たちも村長から呼出状が届くと露骨に嫌な顔をするところから察するに、あまり慕われていない様子である。毎回、この村長への挨拶が鬼門で、無理な要求をめぐって大げんかになることもしばしばなのだが、幸い今回は大きな衝突もなく終えることができた。これでようやく調査の目処が立ったことになる。
もう一つ、忘れてはならない大切なことがあった。ワイワイプロジェクトについての告知である。船の出発までは約1ヶ月しかなく、輸送する商品の確認など、できるだけ早く動き始める必要があった。イヨンジ村の住民組織はワンバ村の場合とは異なり、いくつかの村にまたがる大きな組織ADI(Association pour le Développement d’Iyondje 「イヨンジの発展のための組織」)があり、その傘下に小規模な組織が入っているという、階層型の構造になっている。ヤリサンガで僕たちがお世話になっているパパ・ジャンマリーや、二つ隣の集落に住む日本人との親交が深いパパ・エドワールはADIのコアメンバーである。それ以外にも、二つ隣の集落で懇意にしているパパ・ガリは住民組織の活動に熱心である。彼らに挨拶がてらプロジェクトの話をしてみると、ついにそのときが来たかと好意的な反応が返ってきた。一方、持って行く商品を集める期間が短いから、あまりものが集まらないかもしれないという声も聞かれた。その言葉にやや不安を覚えたが、ADIの他の支部のメンバーや傘下の住民組織に対するプロジェクトの告知と商品の準備を依頼し、いよいよ森のキャンプへ向かうことにした。
いざ、森のキャンプへ
8月15日の朝、木村さんや同行するヤリサンガの住民たちとともに森のキャンプへと出発した。今回は本格的な調査の前の予備調査であり、2泊3日で森のキャンプの様子を確認したあと、いったん村に戻って準備を整えて再度森に入ることになっていた。目的地は、ヤリサンガの南、直線距離で約20キロメートルの森の中に位置する、「カンガ」というキャンプである。「カンガ」とはボンガンドの言葉で「呪術師」を意味する。このキャンプを拓いた人物はもう死んでしまっているが、彼が呪術師であったのかもしれない。同行してくれる彼の息子モバンギシは、彼から学んだのだろうか、森の木々とその薬効、狩猟の方法などに精通した人物である。ちなみに、この「モバンギシ」というのはリンガラ語からとったあだ名で、「人を怖がらせる者」という意味である。ボンガンドの人びとは、本名よりあだ名やクリスチャンネームで呼び合うことを好むが、彼のように一風変わったあだ名を持つ人も多い。
村から南に広がるキャッサバ畑を抜け、森に入る。しばらく進むとイソロンボンゴという川幅1メートル程度の小川にあたり、その中をスネまで濡れながら歩いて行く。徐々に水深が深くなり、膝下に来たあたりで前方に2艘の丸木舟が浮かんでいるのが見えた。ここが、イソロンボンゴの船着き場らしい。その場で細い低木を切り倒し、適当な長さに切って丸木舟の内側につっかえ棒のようにしてはめ込む。丸木舟の底には水がたまるために、荷物が濡れないように上げ底しておくのである。同じ要領で、僕が座る場所も作ってくれた。1艘につきこぎ手が3人乗り込んで出発である(写真2)。

写真2.丸木舟での移動。川幅は十数メートルで、酷く蛇行している。

写真3.前方に倒木あり。どうやって通るのかと思うが、舟は水面からそれほど出ていないため、舳先が通れば通過できる。このときは、先頭のこぎ手が倒木を掴んで無理矢理舳先を沈めてくぐらせ、後ろのわれわれは丸木舟の中に寝そべって無理矢理通過した。ときには、舟を倒木の下にくぐらせて、人間は木の上を越えて通ることもある。

写真4.川岸のキャンプ。このように、川に面してキャンプが作られている場合もある。舟を下りればすぐにキャンプなので便利かもしれないが、虫刺されに悩まされそうである。

写真5.キャンプでの調理の風景。男たちは、幼い頃からキャンプなどに同行して鍛えられているため、獲物の解体から煮炊きまで、一通りの調理ができる。美味しいが、塩やトウガラシで味付けしただけの豪快な、いわばオトコの料理である。味付けの繊細さや主食であるキャッサバの調理は、やはり女性に軍配が上がる。
22時半頃、不意に目が覚める。雨はもう上がったようだ。しかし、サラサラという音が近くで聞こえる。半分寝ぼけながらヘッドランプをつけてみてギョッとする。テントの内部を無数のアリが蠢いているではないか!これは、サスライアリの一種で、現地ではバヒンバと呼ばれる。彼らは黒々とした河のように大群で押し寄せ、進路上の動く物を片っ端から平らげて過ぎ去っていく。人間のように大きな生き物でも関係なく、平気で噛みついてくるうえ、一度噛みついたら死んでも放さないような非常に獰猛なアリである。テントの入り口は固く閉じてあったのにどこから入ってきたのだろうと目をこらしてみると、側面に無数の穴が開いている。恐ろしいことに、テントを食い破って入ってきたのである。急いで殺虫剤をまいてテント内のアリを撃退し、恐る恐るテントの入り口を開いて、思わずうめき声を上げてしまった。僕のテントは彼らの進路上にあるようで、テントの周囲をゾロゾロと黒い河が流れていくのが見えた。こうなると、殺虫剤をまこうが何をしようがこの流れは止まらない。諦めてテントの中でおとなしく横になって目を閉じた。幸い、これ以降テントにアリが入ってくることはなかったが、落ち着かない夜を過ごした。
カンガ到着
8月16日、目が覚めると既に夜は明けていた。空に太陽はなく、辺り一面に薄く霧が広がっている。昨晩の雨と朝露で重たくなったテントを撤収し、朝食を手早く済ませて出発する。こぎ手たちが、村を出るときに話がついていたはずなのに賃金の交渉をしてきたり、エネルギー切れを訴えてキャンプに上陸して食事をとったりもしたが、概ね快調に進む。徐々に調子が出てきたのか、僕の乗っている舟で一番後方のこぎ手をしていたロフォンボが鼻歌を歌い始めた。村では静かにしていることが多いので全く気がつかなかったが、意外といい声をしている。突然、向かい風が吹き抜けていくと、ロフォンボは、鼻歌のメロディに歌詞を乗せる。
「モペペ・マカシ・エー、ビソ・トサリ・マスワ・エー、トゾランダ・エー…(風が強いなぁ、俺たちは舟をこいで、ついていっているんだ)」
そうこうしていると、徐々に天気が悪くなってきた。さっきの風は雨の前触れだったのだろうか。川で雨に見舞われるのは嫌だなぁと思っていると、川幅がみるみる広くなり、開けた場所に到着した(写真6)。僕の目の前に立っているこぎ手のレバネが、「ヘラに到着したよ」と教えてくれたかと思うと、そのまま川に飛び込んだ。ギョッとしたが、水深は彼の胸元までしかない。「このあたりは、水の少ない時期には陸地になるんだ」と笑う(写真7)。ヘラとは川の名前であり、今回の目的地であるキャンプの目印になっている。ここから入り組んだ森の中の流れに入る。1メートルほどしか幅がなく、木々が両脇に迫ってきているが、器用にすり抜けていく。13時を過ぎた頃に接岸。ここが船着き場になっているらしい。ここから10分ほど木々の間を抜けて坂を上ると、開けたキャンプに到着した。ここが今日の目的地である。僕は、てっきりここがカンガだと思い込んでいたのだが、カンガはもう少し歩いたところにあるらしい。

写真6.ヘラ川の近辺。右奥は湿原のようになっている。ここには、森林性のバッファローが出現するという。

写真7.ヘラ川近辺の一番浅いところでレバネがポーズをとる。このように、膝下までしかないところもある。
8月17日、夜明けと共に起床し、軽く食事を済ませる。昨晩、妻子の様子を見にいったオスカールが、蜂蜜の詰まった蜂の巣をお土産に持って帰ってきてくれた。巣ごと丸かじりすると、甘い蜂蜜が口の中いっぱいに広がり美味である。7時頃にカンガへと出発する。木村さんは、カンガはこのキャンプの「近く」だといっていたが、実際には直線距離で4キロメートルも離れており、しかもアップダウンが激しい森の道である。8時半過ぎにカンガに着いたときには、全身汗だくで、息も絶え絶えという状態であった。タフなこぎ手たちの腕にも、玉の汗が浮かんでいた。全然話が違うやん、木村さん!と思ったのはここだけの秘密である。話をカンガに戻すと、キャンプには持ち主であるモバンギシの家族が滞在していた。彼らは、ヤリサンガの住民の中でも特にキャンプの滞在期間が長いため、しっかりとした土壁の家が建てられている(写真8)。ただし、畑はまだ開いていないらしい。つまり、主食のキャッサバは、村の近くの畑からとれたものをここまで持ってきているということだ。


写真8.カンガ全景。
到着早々、子どもたちが、家の裏の森に仕掛けた罠に大きなヘビがかかっていたというので見にいくことにした。森に入って数十メートルのところで、大きな黒ヘビがハネ罠にかかって死んでいた(写真9)。このヘビは、現地ではビリミと呼ばれ、咬まれれば命はないと大変恐れられている。罠にかかっていたのは体長2メートル以上の大型の個体で、これがキャンプのすぐ裏の森にいたというのだからゾッとする。一緒についてきた大人が、すぐに頭部をナタで切り落とし、地面に埋めた。ヘビはやっぱり怖いのだ。残りの部分はキャンプに持ち帰られ、子どもたちがすぐに解体した(写真10)。あまりにも解体の手際が良いので感心して見ていると、「これがミチョポ(腸)で、これがリコ(肝臓)、こっちはロホホ(気管)だね」と、内臓の説明までしてくれた。気管は食べないようだったが、それ以外はほとんど捨てるところがない。われわれも、切り身と脂身を少し分けてもらった。このヘビは、脂身が多く、煮込むと独特の出汁がでて旨いので、楽しみだ。

写真9.罠にかかっていた黒ヘビ、ビリミ。頭部は既に切り落とされて埋められている。手前のノートは、長辺が20センチ弱であることから、いかに大きなヘビであるかがわかる。

写真10.ヘビを解体する若者。僕がヤリサンガで調査を始めた2011年には、やんちゃなませガキであったが、すっかり頼もしくなった。
調査ならず・・・??
予備調査を無事に終えて、後は本調査を行うのみと思いきや、村に戻ったわれわれを待っていたのはトラブルであった。まず、われわれと同行した舟のこぎ手たちが訴えられ、イヨンジ村の村長に召喚された。訴状は、「ヘラのキャンプに行く」と言っていたのに、カンガまで行ったことを咎める内容であった。これは完全な言いがかりだった。カンガもヘラ川からアクセスするキャンプの一つであり、そもそもキャンプの持ち主が同行していたのだから何も問題はないはずだ。こんな無理な訴えを起こしたのは、こぎ手の一人の弟だった。兄がこぎ手として得た給料の分け前にあずかれなかったことを恨んでのことらしい。当然、訴えは数日後には退けられた。こんな理由で訴えて勝ち目があると思ったのかと理解に苦しむところだが、相手の足を引っ張ることそのものが目的というこのような訴訟がしばしば行われるのも事実である。
もっと深刻だったのは、われわれ日本人調査者と村長の間に発生した、住民への支援の内容についての衝突であった。先述のように、ヤリサンガで長年調査を行っている木村さんは、住民との相談の上で彼らへの援助を行ってきている。問題となったのは、援助の内容について住民と同意した項目を書きだした書類についてであった。従来は、住民と木村さんのそれぞれが同意事項についてメモに残していたのみだったが、2014年からはきちんと書類としての体裁を整え、住民の代表と木村さんがサインをし、それを公認するという意味で村長にもサインしてもらって残すようにしたのである。木村さんはこれをスキャンし、ノートパソコンで閲覧できるようにして持ってきていた。そして、以前に同意した援助項目が着実に実行されていることを説明するために、それを村長に見せたのである。ところが、村長が、そんな書類に覚えはないと言い出したところから話はもつれ始めた。スキャンデータが残っているのだから、彼女が忘れているだけなのだが、それを頑として認めようとはしない。それどころか、スキャンデータは、木村さんがパソコンで偽造したと言い出す始末である。この騒動が起こったときには、間の悪いことに、着任して間もない郡長がイヨンジ村の視察に来ており、彼も村長の肩を持った。ヤリサンガ住民の代表までもが、サインをした記憶がないと言い出す始末であった。もっとも、村長と郡長が意見を同じにしている以上、ヤリサンガ住民の代表にはそれを覆して木村さんに同意するという選択肢はなかったのだと思う。下手に逆らえば、何か適当な理由をつけて逮捕されてしまう可能性もあるのだ。さらに、村長はヘラのキャンプに行くといいながらカンガに行った件について、自分は許可していないと再度蒸し返し始めたのである。
無念の撤退
こうして、理不尽にも2014年の書類は否定され、森のキャンプの調査自体も村長の横やりのために危うくなってきた。この後、数日間にわたって何度も説明と交渉が行われたが、議論は堂々巡りであった。おそらく、こちらが折れて2014年の書類はなかったことにして、書類を新しく作ることに同意すれば、問題は収束したと思う。しかし、そうやって作った新しい書類を、数年後に再度否定されないともかぎらない。何より、村長も郡長も、金で手を打とうと思っているのが透けて見えていた。このような横槍を許していては、今後の調査に支障が出るのは明白であった。
このような状況をうけて、木村さんと僕は相談の上、イヨンジ村から撤退し、ワンバ村の基地へ戻ることに決めた。苦渋の決断であったが、ワンバ村でも森のキャンプの調査は可能で、調査としてはリカバリーできる。この決定を聞いて驚いたのは、ヤリサンガの住民たちであった。子ども以外の村人がほとんど総出で、われわれを説得し、翻意を促すために訪ねてきた。ヤリサンガの住民とは大きな問題もなかったのだから、当然の反応である。しかし、われわれは心を鬼にして村を後にしたのだった。
こうして、僕の森のキャンプでの調査は、始まる前から頓挫してしまったのである。フィールド調査には不測の事態がつきものであり、臨機応変に対応することが大事なのはよく分かっているが、今回はさすがに堪えた。ワンバの調査基地への道のりも、いつもは調査を終えて晴々とした充実感に満たされて戻るのだが、今回はひたすら重く沈んだ気分で過ごした。基地に到着後、すぐに松浦さんを交えて今後の調査の打ち合わせを行った。イヨンジでの調査撤退の経緯を聞いた後に、松浦さんはあっけらかんと「心配しないでも、まだまだワンバでやることがあるから」と言った。気落ちしている僕を慰めるために言ってくれているのだと思い、ありがたかった。しかし、後から考えてみると、ワイワイプロジェクトの舟の出港に向けて、本当にやることが沢山あったのである。